会議では、ハノイ天然資源環境大学(TN&MT)学長のホアン・アン・フイ准教授が報告を行い、教育訓練省(MOET)の2021年6月22日付回状第17/2021/TT-BGDDT号に基づいて開発された環境および環境保護ブロックの研修プログラム標準の草案を提示しました。この草案では、大学が環境工学技術、天然資源および環境管理の以下の専攻の学部研修プログラムを開発しています。以下の専攻の大学院プログラム:環境科学、天然資源および環境管理、環境工学。

本校は、環境分野の知識グループに関する天然資源・環境省の要件に従って教科書を編纂するためのリストと計画を調査し、提案しました。同時に、2022年から2023年にかけて専門家や科学者からのコメントを受け取ります。学校は、環境モニタリング(2巻)など、7つの重要な教科書を編集しました。工業および農業部門の環境監査。多様性の保全と生態系の回復;天然資源の評価;循環型経済に向けた持続可能な固形廃棄物の管理と処理。戦略的環境アセスメントと環境影響評価手法。
ハノイ天然資源環境大学は、ヴォー・トゥアン・ニャン副大臣の最終意見に関する通知116/TB-BTNMTの内容に基づき、環境および環境保護分野の研修プログラム基準の基礎レベルの承認を予定通りに実施し完了し、環境分野の学部および大学院の研修プログラム5つを構築し、これらの研修プログラムを教育に導入しました。そのため、2020年の環境保護法に合わせて知識グループを更新するため、ハノイ天然資源環境大学はホーチミン市天然資源環境大学と協力して、2024年から2025年の期間の教科書を編集する予定です。

ホーチミン市天然資源環境大学の学長であるフイン・クエン准教授は、最近、運営委員会の綿密な指導の下、大学は以下の順序でカリキュラムを体系的にまとめたと述べました。ワークショップの構築(カリキュラムの名前、実施計画、カリキュラムの内容の方向性を決定)。カリキュラムの枠組み/概要を開発し、科学専門家との協議を組織する。 2023年3月に予定されている運営委員会会議を通じてカリキュラム案に対する意見を求め、カリキュラム案を作成する。シラバスの草稿を編集します。印刷と出版を進めるため、省庁傘下の二つの学校は教科書を審査する科学専門家のリストを提案し、省庁の科学技術局に送付して、教科書を完成させるための意見を求める草案の承認を待っている。
ホーチミン市自然資源環境大学は、これまでに2023年に編纂予定の教科書案リストに掲載されている教科書4冊を完成させました。教科書は、国内の多くの講師や科学専門家の参加を得て、慎重に編纂されました。この教科書は大学の教材や教育カリキュラムとして使われることを目的としています。

教科書の開発にアイデアを提供した科学技術部のグエン・タック・クオン副部長は、ホーチミン市天然資源環境大学の教科書の開発によって基本的な内容が明確になったと語った。しかし、ハノイ天然資源環境大学の場合、特に環境モニタリングに関する教科書では、主要な内容が明確にされていないため、教科書の論理を保障するためにはモニタリング対象を明確にする必要がある。同時に、予測と警告の目的で、学校は重要な内容が明確にわかるようにフォルダを並べ替える必要があります。
環境省の代表者は、カリキュラムの内容は同省の任務や機能と関連し、合法性を確保する必要があるとコメントした。環境戦略評価及び環境影響評価に関するカリキュラム及び資料を受領した後、省内で討論会を開催します。当省は、フィードバックを提供し、研修カリキュラムの開発プロセスに貢献していただくため、専門家を招聘する予定です。
会議を主導したヴォー・トゥアン・ニャン副大臣は、2つの学校に対し、環境技術、環境モニタリング、環境影響評価、戦略的環境評価、固形廃棄物管理、循環型経済などの問題に関するカリキュラムの内容を、正しい方法と評価プロセスに従って慎重に見直し、予測と警告の研究を提供して、人々に役立ち、科学的研究の成果とカリキュラムを実践できるようにするよう要請した。

省庁が承認したカリキュラムを完成させるために、両校はカリキュラム草案を見直し、各研究の方法論を決定し、各研究の共同著者を明確に特定し、講師、科学者、専門家、管理者、特に天然資源と環境を学ぶ学生の意見を聴取し、学生に既存のカリキュラムを読んでコメントし評価して完成させる必要があります。
副大臣は、環境省と環境汚染管理局に対し、学校から教科書を受け取った後、特に運営委員会のためにそれらの教科書について調査を組織し、コメントを提供して教科書の質を向上させ、不適切な内容、法律、著者に関する問題が起こらないように省に助言するよう指示した。引き続きセミナーを開催し、環境影響評価の専門家や企業を招いてカリキュラムに関する意見を聴取し、草案に必要な追加情報を提供します。カリキュラムを完成させ、それを中核教育プログラムに組み込むことが本校の任務であり責任です。
[広告2]
ソース



![[写真] ホーチミン市の住民は4月30日の祝賀行事を「徹夜で」待っている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/30/560e44ae9dad47669cbc4415766deccf)
![[写真] ハノイは国家統一記念日50周年を祝って明るく飾られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/29/ad75eff9e4e14ac2af4e6636843a6b53)
![[写真] ホーチミン市:人々はパレードを見るために夜通し起きている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/29/cf71fdfd4d814022ac35377a7f34dfd1)

![[写真] ゲアン省:南部解放・祖国統一記念日50周年を祝う賑やかな雰囲気](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/29/64f2981da7bb4b0eb1940aa64034e6a7)











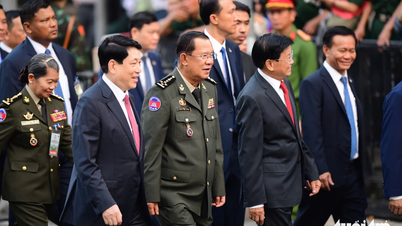








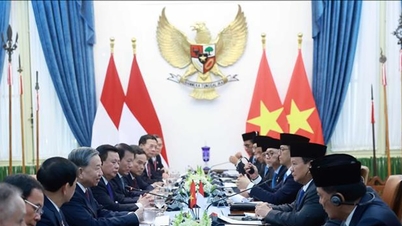




![[写真] ファム・ミン・チン首相が米国との交渉準備のため会談](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/29/76e3106b9a114f37a2905bc41df55f48)







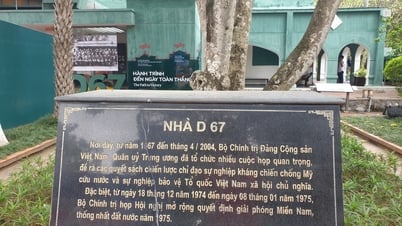






















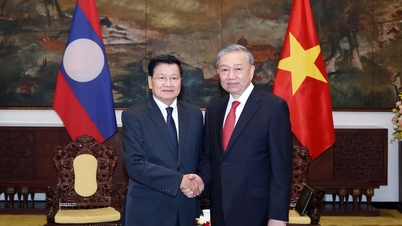

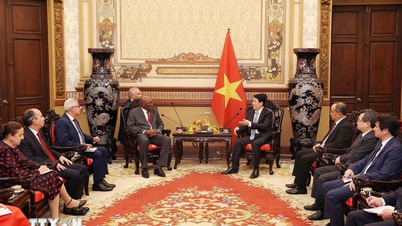







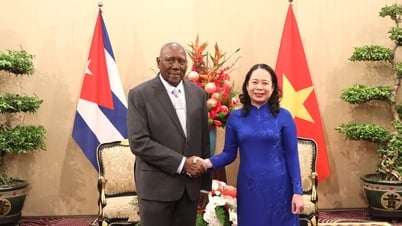




























コメント (0)