税率区分の引き下げと税率の調整に関する提案
3月14日午後、労働新聞社が主催したワークショップ「個人所得税法 ― 公平性の確保、成長の促進」において、国民経済大学銀行金融研究所副所長のファン・ヒュー・ギ准教授は、個人所得税を計算する現在の累進課税表には7段階があり、税率は5%から35%であると述べた。しかし、税率区分が過度に細かく設定されており、区分間の差が狭すぎるため、所得がわずかに増加しただけでも税率と納税額が急激に増加します。

この税制により、中間所得層が高税率層に押し込められやすくなり、大きな経済的圧力が生じ、労働意欲も低下します。
ギ氏は、税率の格差を調整することが合理的な改革の選択肢だと述べた。係数2などの妥当な係数であれば、税制がより安定し、開放性が高まり、所得増加が促進され、中間所得層の労働者が依然として不当に高い税率の対象になる状況が回避されるだろう。
さらに、税率区分の数を 7 段階から 5 段階に減らすことができるため、税額計算システムが簡素化されるとともに、国家予算の歳入が適正に確保されます。
彼は税制を次のように調整することを提案した。
レベル1:所得0~1,000万VND、税率5%
レベル2:所得1,000万~3,000万ドン、税率10%
レベル3: 収入3,000万〜7,000万VND、税率15%。
レベル4: 収入7,000万~1億5,000万VND、税率20%。
レベル5:収入が1億5000万VNDを超える場合、税率は25%です。
ンギ氏によれば、この調整により税制がより公平になり、労働者への経済的圧力が軽減され、予算収入も確保されることになるという。
ギ氏は、特に平均所得が低く、経済が依然として蓄積と投資を必要としている状況において、ベトナムの最高税率は25%で停止すべきだと提案した。現在、法人所得税(CIT)は 20% であるため、適正な個人所得税率であれば労働者のモチベーションが高まります。
「その後、平均所得がより高いレベルに達したら、増税を検討できるだろう」とンギ氏は述べた。
ベトナム税務コンサルタント協会(VTCA)のグエン・ティ・クック会長も同様の見解を示し、現在の最高税率は35%に達し、高所得者にとって大きな経済的負担となっていると述べた。そのため、彼女はこの税率を撤廃し、税率区分間の格差を調整して、税の圧力を軽減し、所得グループ間の公平性を高めることを提案した。
実際にどの程度の所得水準が高いとみなされるかを判断する必要があります。
ファン・ヒュー・ギ准教授は、税額控除は納税者の数と納税額に直接影響するため、個人所得税(PIT)制度において重要な要素であると強調しました。
同氏によれば、課税所得を決定する際には、日々の生活費(交通費、食費、労働再生産)や教育や訓練などの過去の支出など、収入を生み出すために必須の経費を考慮する必要があるという。しかし、現在の税制はこれらの要素を十分に反映しておらず、労働者にとって不公平な課税につながっています。
最近大きな議論となっているものの一つは、家族控除です。現在、この税率は、各州間の生活費の違いにかかわらず、全国一律に適用されています。ンギ氏は、合理的な税制を構築するには、労働者の所得範囲に関する具体的なデータが必要だと述べた。推計によれば、現在、月収1,800万~2,300万ドン(年収8,400~10,500米ドル)の層が労働力の最大の割合を占めている。
「税制を設計する際には、どの程度の所得水準から高い税率を適用すべきかを明確にする必要があります。この基準が不当に設定されれば、大多数を占める中間所得層にも重税が課され、大きな財政圧迫につながる可能性があります。」
そのため、彼は実際の所得状況を反映し、中流階級への悪影響を避けるために、課税所得水準を月額2,000万~2,500万ドンに調整することを提案した。同時に、税制の公平性を確保するため、税制政策においても超高所得層を効果的に管理することに重点を置く必要がある。
さらに、家族控除額の決定は、インフレを反映した消費者物価指数(CPI)、一人当たり所得、最低賃金などの要素に基づいて行う必要があります。これらの数字が大幅に増加した場合、家族控除額も長期間同じままにしておくのではなく、それに応じて調整する必要があります。
財政学院税務学科長のレ・スアン・チュオン准教授は、今後5年間、ベトナムは依然として平均所得の発展途上国のグループに属するため、GDPに比べて比較的高い家族控除を受け入れる必要があると述べた。
彼は納税者に対する個人控除を一人当たりGDPの約1.5倍に相当する額にすべきだと提案した。購買力平価(PPP)でGDPを比較すると、この水準はわずか0.6倍程度で、同様の発展水準にある国々と同等です。同時に、扶養家族一人当たりの控除額を納税者自身の控除額の40%とする原則を維持することを提案した。
また、家族控除額は、消費者物価指数に応じた調整原則に従って毎年決定されるものとし、同時に、税制が経済の実態と一致するように、この調整額の決定権を政府に付与する必要がある。



![[写真] 南朝鮮解放・祖国統一記念日50周年記念式典における文化・スポーツ・メディアブロック](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/30/8a22f876e8d24890be2ae3d88c9b201c)




![[写真] パレードは数万人の人々の腕の中を歩きながら街路に出た。](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/30/180ec64521094c87bdb5a983ff1a30a4)











































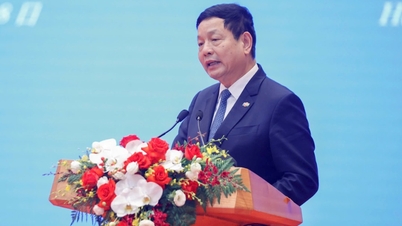

















































コメント (0)