収入は支出ニーズの45%しか満たさない
2023年の労働者の労働状況、賃金、収入、支出、生活の調査と評価の実施に関する報告書を発表する会議で、労働者労働組合研究所(ベトナム労働総連合会)のファム・ティ・トゥ・ラン副所長は、同研究所が6つの省と市の労働者約3,000人を対象に調査を実施したと述べた。
調査対象企業は2022年と比較して従業員数を10%削減した。
調査によると、労働者の52.3%が1日平均1.75時間の残業をしていることが判明した。調査対象となった労働者のほとんどは、収入を増やし生活を向上させるために自発的に残業した。
ラン氏は、2024年も受注不足が続くと予測しており、調査対象企業の17.2%が2023年と比較して2024年の受注不足が拡大すると回答した。
フルタイム勤務を含む基本給は月額600万VNDを超え、2022年3月の調査より8.4%高く、地域によって異なりますが、地域の最低賃金より37.5%~51.9%高くなっています。

労働者労働組合研究所副所長ファム・ティ・トゥ・ラン氏。
2023年の支出は2022年と比較して19%増加し、総支出は月額約1,200万VNDとなりました。このうち、食費に最も多くを費やしており、その割合はおよそ70%に上ります。
調査によると、労働者の24%以上が基本的な費用をまかなうのがやっとで、労働者の最大75.5%が現在の収入が支出ニーズを満たしていないと答え、場合によっては収入が支出ニーズの45%しか満たしていないという。
労働者・労働組合研究所の副所長は、53%以上の労働者が給与を理由に結婚して子供を持たないことを考えていると語った。彼らの給料は都会で子供たちを養うには十分ではないので、子供たちを故郷に送り返さなければなりません。
住宅に関しては、給与の23%以上が家賃の支払いに使われており、電気代や水道代を含めて平均180万VND/月となっています。
なお、調査に参加した157社のほとんどが給与体系を設けており、最低水準は地域の最低賃金と同等となっている。
地域の最低賃金を決定する際に、危険作業手当と訓練手当という2つの手当を除外している企業は23.4%あった。ほとんどの企業は政府の法令に従って地域の最低賃金を調整しましたが、10.1%は依然として6%を下回る調整を行いました。
増加なし…ありえない

ベトナム繊維・衣料労働組合副会長、グエン・タイ・ズオン氏。
ベトナム繊維・縫製労働組合のグエン・タイ・ズオン副会長は、組合幹部は労働者が仕事を得て収入を増やすことを望んでいると語った。
しかしながら、近年、企業は多くの困難に直面しています。今年の最初の6か月間で、繊維・アパレル業界の輸出額は20%以上減少し、その額は40億ドル近くに相当します。職を失った労働者の数は60万人を超えた。
現実には、受注は他国に移り、価格競争も激しくなっている。今年の最初の6か月間で、処理単位の価格は30%以上減少しました。
ドゥオン氏は、これは労働者の賃金と、近々交渉される最低賃金に関係しているだろうと評価した。
「製品に基づいて賃金を計算していない産業では、地域最低賃金の調整時に、新たな賃金体系が製品コストに組み込まれます。そこから賃金基金が増加し、基本的に労働者がこの賃金上昇の恩恵を受けることになります」とドゥオン氏は分析した。
しかし、製品別に給与を算定する単位では、加工単価に応じた給与体系が約6割を占めています。加工価格が下がり、産業の労働生産性が上がらない場合、地域最低賃金を調整しても労働者の実質所得には影響しません。
ベトナム繊維・縫製労働組合副会長は、今回の給与調整は主に社会保険の対象となる給与部分の増加だと述べた。この金額が増加すると、企業は従業員の収入が減少する可能性があることを計算する必要があります。
ドゥオン氏は、今後の地域最低賃金交渉において、市場価格など賃金上昇のマイナス要因を考慮し、比較する必要があると述べた。 「給与はまだ支払われる兆候はないが、物価上昇は明らかに労働者の生活に影響を与えている」とベトナム繊維・縫製労働組合の副会長は語った。
この人物は、来たる賃金交渉の前に、インフレを補うために最低賃金の引き上げ額を計算する必要があると述べた。 「いかなる増加も認められない」とドゥオン氏は断言した。
この人物は、地域最低賃金を満たしていない人に対して地域最低賃金を引き上げることには意義があると分析した。地域の最低賃金を満たさない従業員を抱える企業の中には、より高い賃金を払っている従業員の給料で補わなければならないところもある。
しかし、今年最初の6か月間の繊維業界の平均給与が1人当たり880万ドンであったなど、給与が高い労働者にとっては、給与が増加しても実質所得は増加しなかった。
しかし、政策体制を享受する際の労働者グループの権利を確保するため、ドゥオン氏は依然として企業と労働者の利益を調和させる合理的な値上げを提案した。
[広告2]
ソースリンク






![[写真] ビントゥアン省では4月30日と5月1日に多くの特別な祭りが開催されます](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/1/5180af1d979642468ef6a3a9755d8d51)
![[写真] ハザン省:ホリデーシーズン中に多くの主要プロジェクトが建設中](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/1/8b8d87a9bd9b4d279bf5c1f71c030dec)













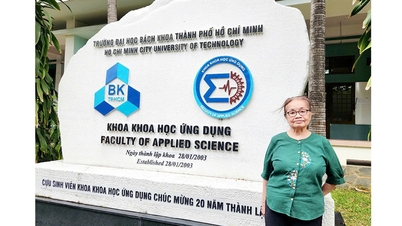


























































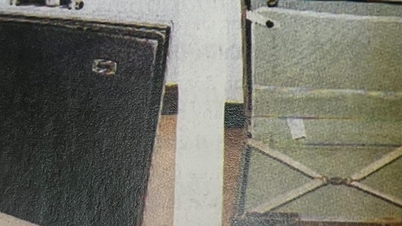




















コメント (0)